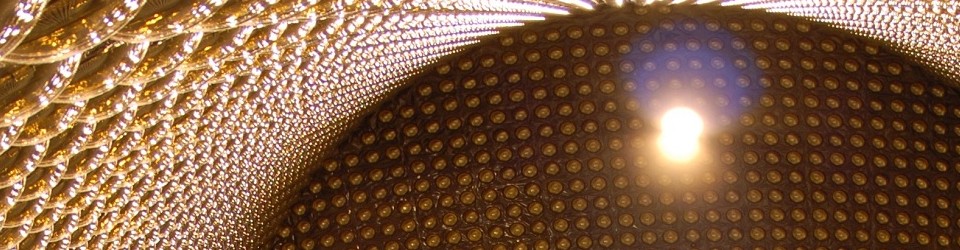村が観光客であふれているゴールデンウイークにバスターミナル付近をハチと散歩していたら、何十年ぶりかに思い出したことがありました。そういえば若かりしころ、観光地で暮らしてみたいと思っていたんだ、って。
観光地へ行く度に思っていたのが、こちらとしては非日常なのにその観光地で生きる人にとってはごく当たり前の日常なので、それが何だか羨ましかったんですね。けど、気がついたら今や望み通り観光地で暮らしていたんでした。
ただし、ボクが憧れていた観光地というのは風情あふれる昔ながらの町並みにお土産屋さんが連なる旧宿場町とか、あるいは歴史を感じさせる屋敷なんかが残っている城下町みたいなところであって、リゾート地ではないんですけどもね。まぁそれはいいや。一番好きな白馬村で暮らせているんだから。
ハチが6月20日で16歳になりました。
せっかくなので記念撮影をと思っていたんですけど、山と青空が揃わず写真がなかなか撮れません。
6月に入り5~7日の3日間は快晴でしたが、その後は昨年と同様に空は晴れていても山は雲の中に隠れていたり雨の日が続いたり、山は見えてるのに空が曇っていたりして週替わりに咲く花々の写真さえも撮ってません。背景に白馬連峰と青空が写らないので。
それに村役場からは熊出没情報のメールが頻繁に届き、森の中に咲く花や木の実を探しにも行けなくなってしまいました。赤い実のヤマグワなんて本当に可愛いです。ヤマボウシについては人里にもたくさんあるので、やがて実をつける姿は熊の心配なしに楽しめそうですけど。
まぁそんな訳で、晴れ渡った6月初旬(5~7日)の景色を今さらながらですけど見ていただくことにします。
春の花々が終わったら村はツツジやアヤメに彩られて見事でした。
ツツジがあちこちで見られるのは当然といえば当然なんですが、どうしてこれほどアヤメがいたる所に咲いているのか不思議です。大町市で見かけた畑なんて、一面すべてがアヤメに埋め尽くされていて圧巻でした。
ただしそれらが本当にアヤメなのか、ひょっとしたらカキツバタかもしれず、ハナショウブだって咲いているだろうし、ノハナショウブも忘れちゃいけないぜってことで判断できずにいます。
アパートの裏に花屋さんがあるので(正確には国道に面した花屋さんの裏に我がアパートがあるんですけど)、アヤメとカキツバタとハナショウブとノハナショウブの見分け方を聞きに行きました。けどパートさんしかいらっしゃらず「私も判らないんですよ」と。
アヤメは花びらに網目模様があるので判断がつきそうなもんですが実際は微妙なものもあり、その微妙さは図鑑でもネットでも判りませんでした。
駅裏の畑に咲く黄色いアヤメかカキツバタかハナショウブかノハナショウブと、道沿いに咲く紫色のアヤメかカキツバタかハナショウブかノハナショウブ(写真 1・2)
見分け不能なア・カ・ハ・ノが満開になるのと同じころにはルピナスも見頃になっていて、あちこちで見かけましたが背景にアルプスがうまく収まるのはここが一番でした。リゾート地っぽい景色でしょ、スイスみたいな。
ルピナスと白馬三山+小蓮華山(写真 3)。
この白い花も短期間ですけどあちこちで目立っていました。名古屋では見たことがないようにも思うんですが、咲いていたのでしょうか。
図鑑で調べたらオオデマリっぽいのでそうしておきます。
五竜岳と見事に咲き誇るオオデマリ(写真 4)。
雑草です。これまで特に意識を向けたことなどなかったヒメジョオンですけど、こちらのは薄ピンク色で可愛いです。
ヒメジョオンの中に混じっている背の高いスイバなんて雑草の王様みたいな存在で、名古屋のころは畑や庭で見つけたらすぐさま排除してました。ところがこのスイバの根っこがゴボウのように太いし木の根のように硬いため、先端が三角に尖った鍬のような殺草兵器で思いっきりぶった切らないとすぐに再生してしまって本当に厄介な存在だったのに、こちらで見かけると何だか健気に見えてくるのが不思議です。自分の畑じゃないからでしょうけど。
雑草と白馬三山+小蓮華山(写真 5)。
最後は待ち焦がれていたタチアオイです。ハチの誕生日(20日)ごろから咲き始め、ついに28日の朝は山と(半分、白い)青空(=半分、青い)がなんとか揃いました。
花としては白馬村へ来て一番の衝撃だったのがこれです。最初はハイビスカスかと思っていたので、ここは沖縄かって一人ツッコミしてました。去年の今ごろのことです。
色鮮やかなタチアオイと初夏の白馬村(写真 6)。