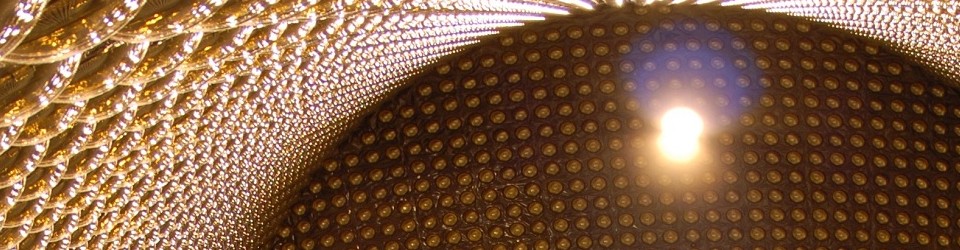今年も田んぼ鏡(鏡田んぼ?)の季節がやってまいりました。そこら中の田んぼが鏡になり、一番のお気に入りは白馬駅裏にあります。
昨年も同じ場所から同じ角度で撮っていて、比べてみると今年はドカ雪が続いたのでまだ残雪も多く、その差がはっきりと確認できました。
快晴+雲ナシ+風ナシ黄砂ナシ(+できれば前日に雨が降って上空に舞っていたホコリが流されていれば空がより青くなってさらに良し)といった好条件が揃うことは稀で、今年は5月8日がその日になりました。
残雪多き今年5月8日の田んぼ鏡と、残雪が少なかった昨年5月10日の田んぼ鏡(写真 1・2)。
この時期、白馬村では春と初夏がしばらくの間は同時進行しまして、昨年の絶好田んぼ鏡日和(5月10日)の朝は放射冷却によって冷え込み最低気温は-0.5度の冬日。日中は23.9度まで上がって夏日のやや手前で暑い暑い。暑いけど八重桜は満開だしヤマザクラもまだまだ残っていて春は終わってません。ませんけど陽射しは初夏で半袖じゃないとやってられず、春と初夏が重なっているんです。縄文時代と弥生時代が重なっていたように。
縄文時代は紀元前千年~紀元前三百年ごろを晩期としてこれで縄文時代が終わるんですが、弥生時代も紀元前千年ごろから始まっていたので同時進行でした。けど、こんな話は弥栄古代史研究室の管轄ですね。
今年(5月8日)は最低が0.4度で最高が20.7度。一日で冬日と夏日が味わえる二度美味しい日は残念ながら今年もお預けになりました。
写真に写ってる山は北アルプスの中でも後(うしろ)立山連峰と呼ばれる峰々ですが、それは富山県側から見てのこと。
富山県側からだと立山連峰の後ろにある峰々なので後立山連峰と呼ばれているように思われがちですが、そうではなく立山の後ろにも大きな山があり、それが後(うしろ)立山と呼ばれるようになって、その後立山が連なる峰々なので後立山連峰なんです。
けど長野県側からすればどう見たって表側なので白馬連峰と呼ぶほうが好ましいし、かといって長野県側から立山連峰のことを後白馬連峰とは呼んでません。やさしいので。
ちなみに、どの山が後立山なのかは長らく議論されていたようで、以前は五竜岳に比定されてましたが今ではどうやら鹿島槍ヶ岳に落ち着いているとのこと。
五竜岳は写真で一番左の山です。
右から順に白馬岳(2932㍍)・杓子岳(2812㍍)・白馬鑓ヶ岳(2903㍍)、天狗の頭と呼ばれる平らっぽいところを過ぎて唐松岳(2696㍍)・五竜岳(2814㍍)です。
ちなみに、写真で右端の白馬岳からさらに右(北)には小蓮華山(2766㍍)・雪倉山(2611㍍)・朝日岳(2418㍍)などが続き、北アルプスは日本海まで連なっています。
これら白馬連峰の向こう側には雄大かつ幽玄なる黒部渓谷(富山県)が広がっており、切り立った急峻な崖下を縫うようにして流れる黒部川を下流に向かうと宇奈月温泉に出ます。
写真には写ってませんけど五竜岳の左(南)には後立山であろう鹿島槍ヶ岳が聳え、大町からだとよりいっそう迫力ある姿に見えます。けど田んぼ鏡になった写真は迫力のないこれしかありませんでした(写真 3)。
右から、ピークがふたつある鹿島槍ヶ岳(2889㍍)・ピークがどれだか判らない爺ヶ岳(2670㍍)・遠くなので低く見えてしまう岩小屋沢岳(2631㍍)と鳴沢岳(2641㍍)・こんもり大きな蓮華岳(2799㍍)・一番左端は北葛岳(2551㍍)になります。
写真では蓮華岳に隠れてしまってますが、その向こうにある針ノ木岳あたりまでが白馬連峰です。
そして左端の北葛岳から先も北アルプスは続くよどこまでも。
どこまで?
穂高連峰まで。
槍ヶ岳(3180㍍)・北穂高岳(3106㍍)・奥穂高岳(3190㍍)などなど美しくも妖艶な峰々が穂高連峰です。
その穂高連峰は長野県側の入り口が上高地で、岐阜県側が奥飛騨温泉郷や新穂高ロープウェイでして、どちらへもお出かけください。素晴らしいです。
(※資料によっては穂高連峰の先の乗鞍岳(3026㍍)までを北アルプスとしているものもあります)
大町からの写真に戻りまして、低く見えてる岩小屋沢岳や鳴沢岳の向こう側には黒部第4ダム(通称クロヨン)があります。
映画「黒部の太陽」はこのダム建設に必要な資材を運ぶためのトンネル掘り工事のお話しで、171人もの犠牲者を出した世紀の難工事でした。
ダムを歩いて渡るかダム湖を泳いで渡ると正面は立山(3015㍍)です。右ななめ前方には剱岳(2999㍍)が鎮座し、これが立山連峰です。後白馬連峰ではありません。
それにしても剱岳の標高は1メートルぐらい何とかならないもんだろうか。いいじゃん3000㍍で。誰か困りますか?
立山から富山県側へ少し下り、室堂まで行けばあの有名な雪の壁があります。今年の壁は高さが16メートルでした。
他にも安曇野から見上げる燕岳(つばくろだけ、2763㍍)・大天井岳(おてんしょうだけ、2922㍍)・常念岳(2857㍍)・蝶ヶ岳(2677㍍)などが連なる常念山脈も素晴らしく、立山連峰、白馬連峰(後立山連峰)、穂高連峰、常念山脈をひっくるめてが北アルプスです。
なのでボクが白馬村からいつも眺めてる山の景色は北アルプス全体からすればわずか10%かせいぜい15%程度で、ほんの一部だけなんです。
その北アルプス(=飛騨山脈)に、中央アルプス(=木曽山脈)と南アルプス(=赤石山脈)を合わせた総称を日本アルプスと呼びます。
日本は島国ですが素晴らしき山国でもあり、さらに白馬村は雪国だし北海道などはそれに加えて北国でもあり、いろんな国ありすぎて迷う。
白馬村には雪国らしい古民家がいくつも残っていて、この季節は絵になります。古民家の先に望む白馬連峰と、その古民家前を通るハチも好きな散歩道(写真 4・5)。
古民家の手前にある坂を登って左へ曲がると広い畑を貫く田舎道へ出ます。この道はpart 53にも出しましたが春はまぶしいほど色鮮やかなのでヘビさん熊さんに注意しながら季節を楽しんでましたが、そろそろ夏の花に様変わりしそうです(写真 6・7)。