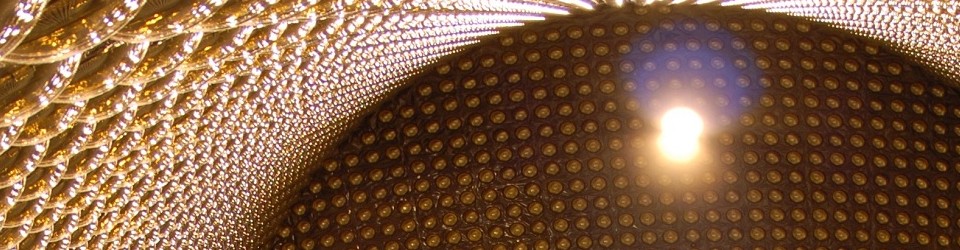9月中旬には最低気温が15度前後になり、ハチの早朝散歩が爽快になりました。22日は9.8度まで下がったので寒かったけど。
そんなわけで本格的な秋の訪れなんですが、山が晴れない。空は晴れているのにアルプスは雲に隠れて姿を見せてくれません。
朝の5時ごろは朝日に輝く勇姿が見られても6時半か7時になると山頂付近に雲がわき始め、8時にもなれば中腹より上部はすべて雲の中。10月になってもです。秋なのに。
東海道新幹線で東京方面へ行くときは必ず E席を予約してましたが夏は富士山が見られません。いつも雲の中。
2022年の夏は5回連続で雲に隠れてました。早くからE席(富士山側の窓側)を確保して楽しみにしてたんだから500円ぐらい残念でしたね返金してほしい。
けど秋になったら5回連続で快晴。山頂までくっきり見事に見られました。幸運でしたね追加金500円ぐらい払いましょうか。
白馬連峰も夏は悲しくなるほど雲に隠れてばかりで、昨年の6~8月はずーっと姿を現さずでしたけど、今年は少しマシだったのでよかったよかった。
ところがです。去年は9月に入ると夜明けから日暮れまで雲ひとつ出現しない秋晴れが何日かありましたが、今年はそれがない。ときどき昼間に姿を現してもくれていても気がつけばいつの間にやら雲が山頂を覆っているので、9月は写真を1枚も撮らず仕舞い。日々是白馬村もほったらかしになってました。
10月に入ってもグズグズ天気は続いていて観光客に何だか申し訳ないです。せっかく来てもらったのに。
ボクに責任があるわけではないけど、三連休とかで3日間とも天気が悪いと謝りたくなってしまいます。ごめんなさいね、アルプスを見せてあげられなくって、って。
用があって村役場へ行ったら入り口に今月1日の人口が8334人になってました。ちょっと減った。土地の価格は爆上がりしてるんだけど。
人口が8千3百余人の村に年間270万人の観光客が訪れ、移住を希望するガイジンが不動産物件を買い漁っているので、10数年前は坪4~5万円だった土地でもエリアによっては取り引き価格が坪50万円を超えました。
けど笑えることに、もっとも地価が上がってる人気エリアはもっとも熊が頻繁に出没していて、熊にも人気みたいです。
役場の農政課から熊目撃情報メールがしょっちゅう届き、そのうち半分ぐらいは人気のMiso……地区やWada……地区ですが、それでも物件が出るとすぐに言い値で売れてしまうそうです。ガイジンが買うんですって。
それはご自由にしていただくとして、京都府は年間の観光客数が8400万人ですってね。
市町村単位では京都市だけで5600万人。大変だ。
鎌倉市も1600万人なので白馬村の270万人って大したことないように思えてきた。
京都市の人口は143万人。観光客が5600万人だから住んでる人の39倍が訪れてることになります。
鎌倉市は人口17.3万人に対して観光客1600万人だから92倍。鎌倉市、ヤバいっすね。
白馬村も計算したら村民0.83万人のところへ観光客270万人。実に320倍で、もっとスゴいじゃんか白馬村。
ということは村民1人に対して年間320人の観光客が来てるわけだから、その観光客から1人につき1万円の純利益を得られれば村民全員が年に320万円の収入を確保できることになる。天丼3980円の店とか牛丼5000円の店とかフライドポテト1650円の店とかへ行かなければ充分に生活できちゃいますね。
問題は、すべての観光客から純利益で1万円ずつをどのようにして得ればいいのかなんですけど、どうすればいいのでしょう。
昼間はアルプスが隠れてるので、古民家が残る新田(しんでん)地区までハチと散歩に行きました。
岐阜県の飛騨地方では合掌造りが知られてますが、白馬村は兜(かぶと)造りです。兜造りは全国の田舎で見かけますけどこれがまた魅力的で、村内には今でも兜造りを新築で設計してくれる建築屋さんも残ってます。
兜造りの家に暮らして長靴姿で軽トラに乗って出かけるオジサン・オバサンがカッコよく、ここのところ軽トラを買おうか悩んでます。ボクは農機具を積むわけではないので軽トラじゃなくてもいいんですが、WBCの栗山監督も北海道の栗山町へ帰ったら軽トラに長靴でしたし、やっぱり欲しい。
学生時代はいつも新田地区の民宿でお世話になっていました。冬休みの合宿だったり国体やインターハイの県予選会で。
久しぶりに歩いてみたら昔からの民宿は姿を変えていましたが、兜造りの民家がいくつか並んでいるので心やすらぐ散歩路でした。
新田地区に残る兜造りの古民家あれこれ。パン屋さんになってる古民家も(写真 1・2・3)。
大出(おおいで)地区の古民家。手前右は一般の民家で、奥は水車が目印のかっぱ亭。ランチが人気のようです。店の前を通るたび気になってるんですが、ハチが一緒なのでまだ寄れてません(写真 4)。
とはいえ兜造りで有名なのはpart 44でも紹介しましたが青鬼(あおに)地区です。田植えの季節になるとヒッチコックの「鳥」ぐらいカメラマンだらけになります。盛りすぎてますけど。
朝霧にけむる集落と昼下がりの眩しい集落(写真 5・6)。