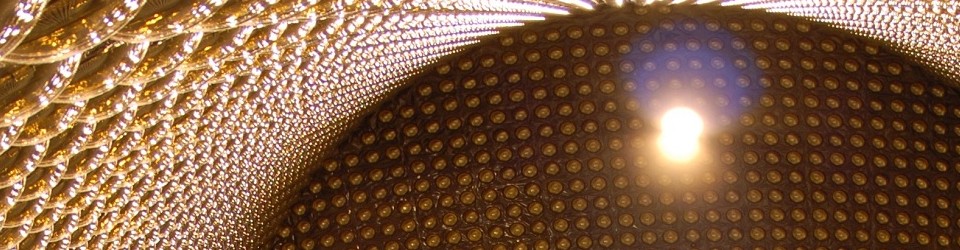だんだん天武天皇から遠ざかっているような気もしますけど、諏訪の歴史を判らずして信濃への陪都は理解できなさそうなので、しばらくは諏訪を再考します。
縄文時代の中期、日本でもっとも人口が多かったのは諏訪湖を中心とした地域だったそうです。
特に諏訪湖北側の蓼科山麓には当時の集落跡や遺跡が次から次へとわんさか見つかっていて、標高1700~1800メートルの山の中腹や山頂付近にも大勢が暮らしていました。
縄文中期は温暖な気候だったのでしょうか?
いえいえ、そんなことはなく、寒かったらしいです。
ではナゼ人々は山の中へ中へと移動したのでしょうか?