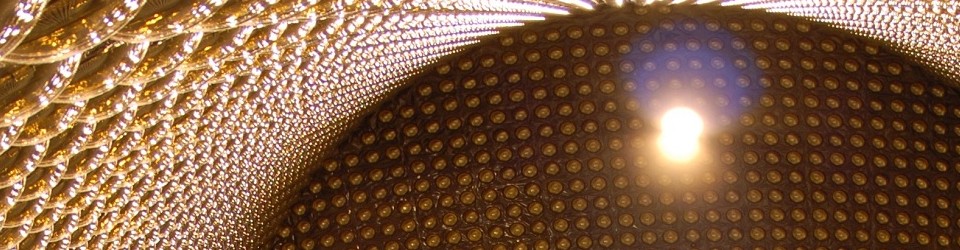下諏訪町東山田地区にある熊野神社の小宮御柱に総勢22人で参加させていただきました。
この熊野神社は和田峠(日本でもっとも美しい黒曜石が採れる峠)の守護神でもあります。
ルパン三世笠原大総代が棲まう岡谷市川岸の熊野神社(小宮御柱祭り 第6弾)は旧中仙道の小野峠(三沢峠)を守護する神なので、熊野神社は峠を護るハタラキがあるようですね。
さて、北は仙台、東は宇都宮や神奈川、西は大阪、南は熊本からの参加者をお連れしたところ、まぁ大総代の林さんも区長の高木さんも曳行長さんも役員さんも氏子さんも受け入れ準備が完璧でして、これほど歓迎していただけるとは思ってもみませんでしたので、参加者一同大感激でした。
下諏訪町東山田地区熊野神社の氏子の皆様、あたたかいお心遣い本当にありがとうございました。