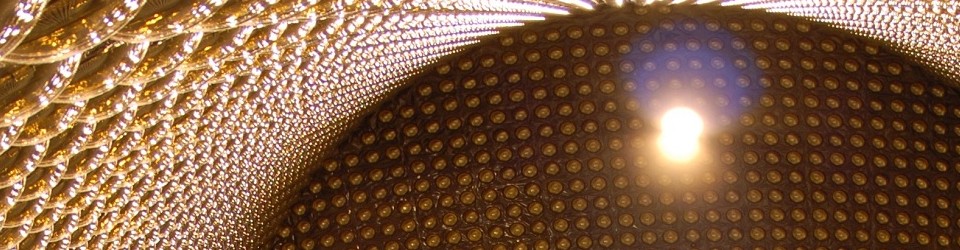小宮御柱祭りの第3弾は茅野市湖東(こひがし)の中村地区にある大星神社です。
この地区は茅野市の湖東・北山・米沢の三地区で結成されている「三友会」のエリアなので、とても楽しみにしていました。
結論から言うと、三友会はラッパ隊の規模も出しものの完成度も素晴らしく、実は他の地区から”ヤリ過ぎだ”と非難さえ出るほどなんですが、大星神社でも小宮御柱祭りとは思えないパフォーマンスを披露してくれました。
ボクのガラケーは待ち受け画面が三友会なので、それを見せると皆さん喜んでくださり、さっそく記念撮影。(写真1)
「弥栄整体のお話し会in浜松」
11月12日、浜松で骨や筋肉と健康の関係についてのお話し会があります。
主催者さんがていねいな案内文を出してくださったので、そのままお伝えいたします。
ですから浜松へ行ったら”さわやか”のハンバーグが食べたくなるという話はまた今度にします。
「小宮御柱祭り 第2弾」
第2弾は茅野市玉川地区の小泉諏訪神社で御柱を曳行させていただいたんですが、氏子さんの人数が少なくて御柱がちっとも動かずに大変でした。
楽しかったけどもこんな動かない御柱は初めてで、スタート直後にはどうなることかと本気で心配しました。
なにしろこの地区の曳行はずーっと登り坂でして、しかも境内に曳き入れる手前には恐ろしく急な坂があり、メドテコをつけたままで狭い鳥居をくぐり抜けつつ急な坂を登るもんだから、社の前に曳きつけたころにはもうヘトヘトで腹ペコでした。
メドテコを外せば苦労なく曳き上げられるのに、それをせずに困難な道を選ぶ諏訪の氏子は、ちょっとイカれてますけどカッコよかったです。
「テキスト写真集」
お待たせしておりましたが、技の解説付き写真集が完成しました。
カラー・モノクロ織り交ぜた全100ページで、5級クラスと4級クラスで習う技のほとんどが解説付きで紹介されているため、復習するのに便利だと思います。
各教室でも販売しますが、すでに卒業された生徒さんは郵送もいたします。
生徒および卒業生に限りの販売になり、生徒価格の税込み2000円。(郵送の場合は送料が必要です)
☆写真1:すべてはこの三角形から始まります。万里の長城の両端と喜望峰(右肩甲骨の場合はマゼラン海峡)を結んだ弥栄トライアングルで、その中央エリアが肩甲骨の2番になります。
「諏訪古事記 その19」
まずは小谷村役場では連日お世話になりまして、ありがとうございました。
薙鎌神事は諏訪大社から宮司が小谷村まで出向き、6年おきの御柱祭り前年に新潟県との県境にある社でおこないます。
薙鎌を御神木に打ち付けるのは小谷村戸土(とど)の「境の宮諏訪神社」と小谷村中股の「小倉明神社」の2社があり、毎回交代でおこなうためにそれぞれの社にとっては12年に1度の行事になります。
それでその社、両社ともとんでもない山奥にあるため役場の柴田さんから詳しく聞いておいてよかったです。役場へ寄らなければ絶対にたどり着けませんでしたし、小倉明神社に至っては一般車輌進入禁止なんですけど看板に気づかなかったことにして…………
「諏訪古事記 その18」
ヌナカワヒメを探りに新潟県の糸魚川へ行ってきました。
糸魚川のヒスイは出雲や九州でも見つかっているので古くから全国各地と交易があったのかと思いきや、縄文時代の後期中葉(約4000年前ぐらい)までは東北~中部の東日本だけが流通域で、まだ出雲や九州など西日本へは行ってなかったんですね。
文化の中心が西日本に移るのは弥生時代からで、縄文時代は遺跡の数だと圧倒的に東日本のほうが多いですし、話題性のある魅力的な縄文土器はすべて東日本で出土しているので、”縄文の東日本、弥生の西日本”はヒスイの流通からも知ることができました。
そんな糸魚川からある時代になるとヒスイ製品も職人集団も突然消えてしまったんです。
ヤマト朝廷の仕業かっ!
「諏訪古事記 その17」
「遷都信濃国」で何度も取り上げましたが、なぜ諏訪は信濃国から独立させられたのでしょうか?
それは天武天皇の意志を継いだ長屋王の思惑によるものだったか?
また、諏訪を好意的に保護しつつ律令制の整備が目的での諏訪国独立か、それとも朝廷に従わない”まつろわぬ者ども”を敵対視して隔離するためなのか。理由がどちらなのかによって導き出される答えが正反対になります。
長屋王が即位していたか否かは別として、実権を握っていたのが721年1月~729年2月まで。2月12日に自害したことになっています。実際は妻子4人と一緒に殺害されたのでしょうけども。
「祝 41」
“リオ”って数にすると「47」で、「47」は都道府県の数であり、いろはにほへと………が47音、ひふみよいむなや………も47音なので、日本人に関わるどんな数が出てくるかを楽しみにしていたところ、メダルの数が「41」でした。
「41」はミロク方陣の中心の数であり、”神”とか”信念”とか”才能”なので今さら説明するまでもありませんね。
おめでとうございます。
それと、選手の皆様。日本の代表になるだけでも尊敬するに値(あたい)しますので、結果について謝るのはやめてください。誰一人として責めていないと思います。
「諏訪古事記 その16」
アイヌとオタリ村(長野県北安曇郡小谷村)が結びつき、他にも調べなければならないことがあるため久しぶりに白馬村・小谷村方面へ行ってきます。
そして今回は県境を越えて翡翠の産地新潟県の糸魚川へも。タケミナカタの母であるヌナカワヒメのお里ですが、翡翠を産出する姫川の古名は”ヌナ川”といい、だとするとタケミナカタの母がヌナカワヒメなのではなく、タケミナカタの生まれた地がヌナ川(糸魚川)近辺なのかもしれないですね。
すると出雲はどうなるんだと疑問がわきますが、諏訪入りしたアイヌ人は日本海側から来たとも考えられるため、当然のこと日本海側には他の地域にもアイヌ人が暮らしていたとしても不思議ではありません。
「締め切りのお知らせ」
9月22日の名古屋数霊セミナー&ワークと、10月22~23日の諏訪ツアーはいつの間にか定員をオーバーしていましたので、募集を締め切らせていただきます。
ありがとうございました。
尚、諏訪ツアーは御柱を曳くときに手袋(軍手でも可)が必要になりますので、ご持参くださるようお願いいたします。