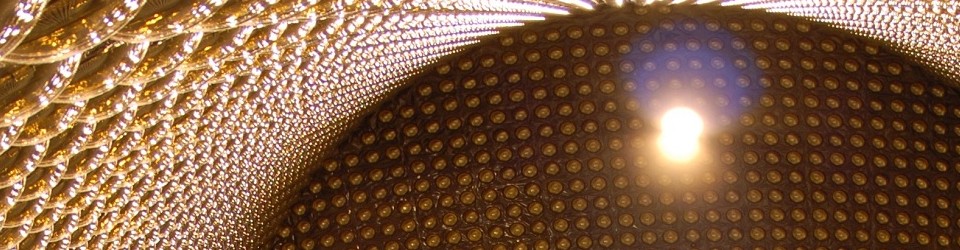仕事以外では頭の中がほとんど諏訪なので、スーパーでレジ待ちをしているとき後ろに並んでいる客同士の会話が聞こえてきて、白髪のおじさんが発した
“そうなんですわ”
の一言に身体がピクッと反応して無意識に振り返ってしまった。びっくりしま諏訪。
土偶「縄文のヴィーナス」や「仮面の女神」が発見された茅野市は縄文遺跡の宝庫ですので、地元の研究家に案内をお願いしました。
それで、尖石考古博物館の館長さんや学芸員さんを紹介してもらいに博物館へ行ったら、学芸員さんは以前にもいろいろ説明してくださった男性でした。
改めて話を伺うとこの学芸員氏が面白かったので、縄文土器のモチーフになっている蛇についてお聞きしました。
「土器の蛇は何を意味しているんですか?」って。